2段階で考える避難
川上:サポートコミュニティ飛騨の川上哲也です。前回は災害時の避難を2段階で考えるという内容でお話ししましたが、先週は春の高山祭でお休みを頂きまして、今週は先々週お話しした2段階の最初の部分、いかに命を守るか、家族とどうやって連絡を取るかについてお話しさせて頂きますね。
遠藤:宜しくお願いします。川上さん、先ずは前回のおさらいからいきたいと思うんですけど、災害時の避難を2段階で考えるということについて、もう一度、簡単にお願いできますか?
川上:はい、災害時の避難については、今まで命を守るという部分と、助かってから後の部分がごっちゃになって教えられていたんですけど、これを1段階目である「命を守る」から「家族間の連絡」までの部分と、その後の2段階目の「避難」及び「避難生活」の2つに分けて考えて、災害発生時は1段階目を優先して考えなければならないということですよね。
遠藤:そうでしたよね。過去の災害では、非常持出袋を準備している間に避難するタイミングを失ったというケースもありましたけど、この非常持出袋というのは避難した後に役立つものですから、これは2段階目のもの。だから、災害発生時はとにかく命を守る、早く避難する、そして家族と連絡を取るということに専念して欲しいということでしたよね。
川上:そうですね。そして今回は、その1段階目についてもう少し詳しくお話しさせて頂きますね。
遠藤:それじゃあ、先ずは「命を守る」について、家族でどんなことを話し合っておくべきなのかからお話し頂けますか?
川上:はい、この命を守るということについて家族で話し合う内容についてですが、地震対策としては、先程お話ししました1段階目の前のゼロ段階と言いますか、事前の対応ということで、安全な家にどうやって改善していくかについて話し合うことから始めて欲しいですよね。
遠藤:安全な家にどうやって改善していくかって、家の耐震補強をするということですか?
川上:家の耐震補強については、お金のかかることですが、昭和57年以前に建築された家にお住まいの方は、一度耐震診断と耐震補強について検討して欲しいですよね。耐震診断は無料で受けれますし、耐震補強についても補助がありますからね。
遠藤:補助の相談については高山市役所に連絡すれば良かったんですよね。
川上:そうですね。さて、この耐震補強についてはそれくらいにしておいてですねぇ、今回はそれ以外の話合いについてお話しさせて頂きますね。
遠藤:耐震補強以外には、どんなことを話し合っておけばいいんですか?
川上:先ずは安全な所に寝ているかを確認して欲しいですよね。リスナーの皆さんにも考えて欲しいんですが、1日24時間のうち4分の1から3分の1の時間は寝室にいるわけですよね。その他の時間はどこにいるかを考えると、8時間勤務の方だったら、24時間のうち9時間から10時間程度は職場でしょ。で、家の中で食事をする部屋には何時間、テレビがある部屋には何時間って具体的に考えていくと、やっぱり寝室にいる比率がかなり高いことがわかるんですよね。地震はいつ起きてもおかしくないですから、地震にあう確率の高い寝室をいかに安全にしておくかということも、命を守ることに直結するわけですよね。
遠藤:確かに寝室にいる時間って長いですよね。そして、寝てる時って無防備ですから、やっぱり安全にしておくって大切ですよね。
川上:そう、寝室では上から落ちてくる物、倒れてくる物を最小にしておくことも必要ですよね。タンスや本棚はできるだけ寝室以外に持っていくとか、家族で考えて欲しいですよね。それと、寝室の位置についても少し考えて欲しいんですが、阪神淡路大震災や中越地震などで倒壊した家を見ると、2階建ての住宅でしたら、1階部分が倒壊して2階部分がその上に落ちてきたというものも多かったんですよね。この他に、全てが倒壊したというものもありましたけど、先ほどの場合とは逆の、2階部分だけが倒壊して1階部分は残ったというものは少なかった…と考えると、倒壊の危険性がある建物だと、その家のどこだったら命が奪われ難いかについて考えて欲しいですよね。
遠藤:確かに1階部分だけが倒壊した写真は何度も見ましたけど、2階部分だけが倒壊して1階が残った写真というのは見た記憶がありませんよね。
川上:でしょ。そして次にはですねぇ、命を守るため安全な所へ迅速に避難するために、避難路となる廊下、階段を安全にしておく。物を置かない、ガラスなどにはフィルムを貼っておくということですよね。災害が発生すると頭の中がパニックになってしまうことも多くありますから、パニックになっても避難できるような状態にしておくことが必要ですよね。
遠藤:川上さん、話が少しそれるかもしれませんけど、一人暮らしのお年寄りの方に対しては、まわりの方が家の中の対応まですべきなんでしょうか?
川上:その一人暮らしの方がどういった方かにもよりますけど、自分の力でスタコラサッサと避難できない危険性がある災害時要援護者だという場合でしたら、できればまわりの方が寝室の安全性と、家の中の避難路の安全性を確認して欲しいですよね。個人のプライバシーに関わる内容ですから難しいかもしれませんが、過去の震災では、寝室の位置がわかっていることによって助かった命もあるわけですから、地域で命をいかに守るかについて考えて欲しいですよね。赤ちゃんや小さなお子さん、そしてお年寄りなど、自力で対応できない、或いは対応力が弱いと思われる方には、できるだけ安全な所にいてもらう、そしてイザという時に備えておくことが必要ですよね。
遠藤:川上さん、今日は1段階目の前のゼロ段階というか、地震対策のうち、事前にやっておくべきことが中心になりましたけど、この他に、事前にやっておくことってどんなことがあるんですか?
川上:災害発生時の避難の1段階目の内容である、命をいかに守るか、家族との連絡について話す予定が、事前のことだけで時間がきちゃいましたよね。さて、この他にやっておくべきことですが、万が一倒壊した家の下敷きになった方がある場合、救助作業を行わなければなりませんので、もし可能であれば、バールやジャッキなんかを用意しておくといいですよね。ジャッキは、車のタイヤ交換で使うようなものでも役に立ちますから、中古車として出す場合はだめでしょうけど、もし、車を廃車にするような場合でしたら、ジャッキだけよけておけばイザという時に役立ちますよね。なんだか、本題に入れずに終ってしまいますが、とにかく、とにかくですねぇ、地震が起きた時、安全に家から出ることさえできれば、かなりの命が救われるわけですから、生きて家から出るためにはどうしたら良いのかということをテーマに、是非是非、家族で一度話し合って欲しいですよね。
来週こそは、先日お話しした1段階目である「命を守る」と「家族との連絡」についてお話しさせて頂きますね。
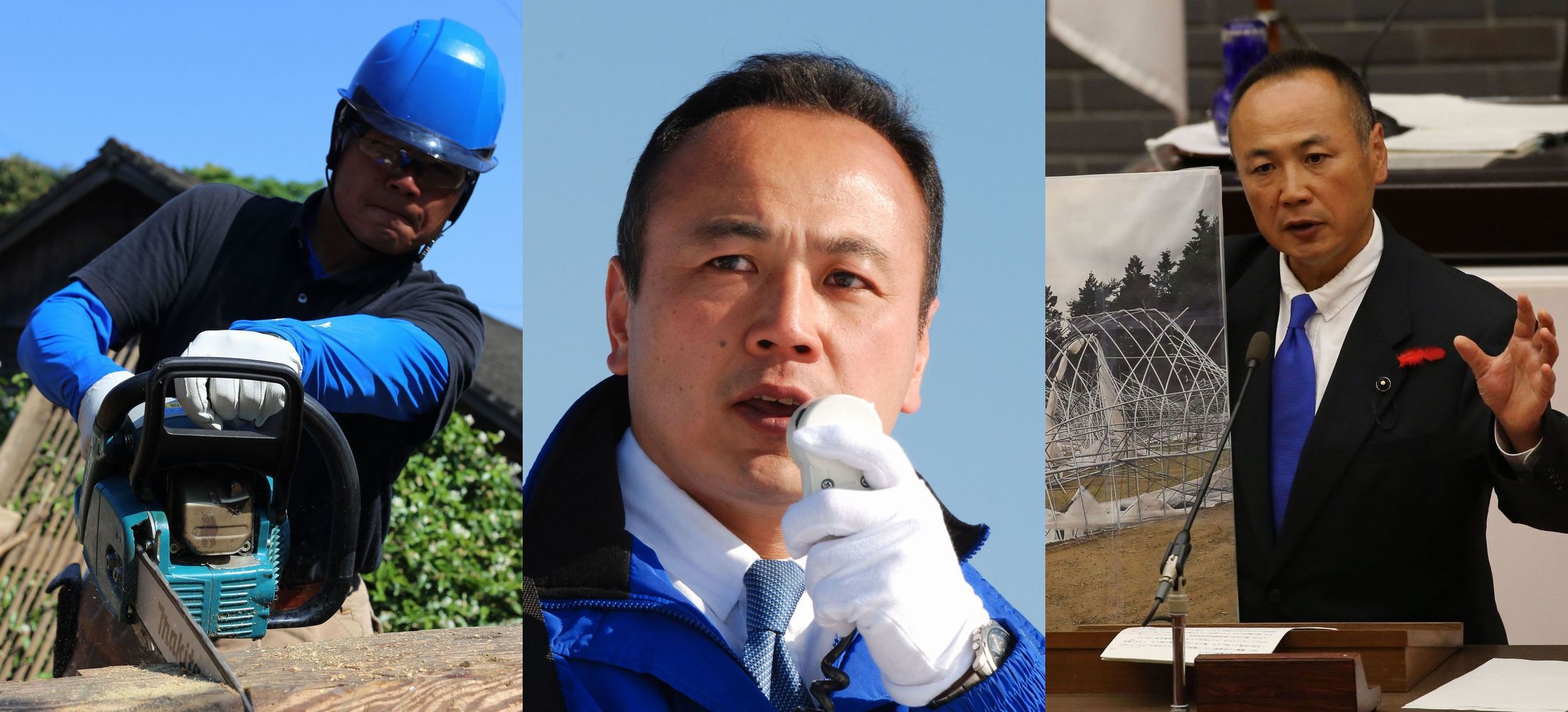



 4月8日放送
4月8日放送 川上:サポートコミュニティ飛騨の川上哲也です。さて遠藤さん、今朝はビックリしました。
川上:サポートコミュニティ飛騨の川上哲也です。さて遠藤さん、今朝はビックリしました。