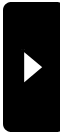高次脳機能障害
 今日も、長男に作ってもらったイラストで…。
今日も、長男に作ってもらったイラストで…。今議会、一般質問の中で、景気雇用に関する項目以外に、「福祉」についても取り上げたいと思っています。
今回取り上げるテーマは「高次脳機能障害」。
事故や脳血管障害などによって、身体に障害が残ることがあります。
そのリハビリが終わり、さあ職場へ復帰…となった時、目に見えない障害(例:認知障害など)が残っていたため、離職に追い込まれるということも少なくないようです。
現在は、高次脳機能障害に対する認識が低い(医療機関でも見落とされることがあります)ことに加え、急性期治療後の支援システムが整っていないことにより、なかなか社会復帰が難しい状態となっています。
身体的に不自由なく生活できている方も、いつなるかわからないこの傷害に対して、ソフト対策だけでも充実すべきですよね。
一般質問後に、またご報告させて頂きます。
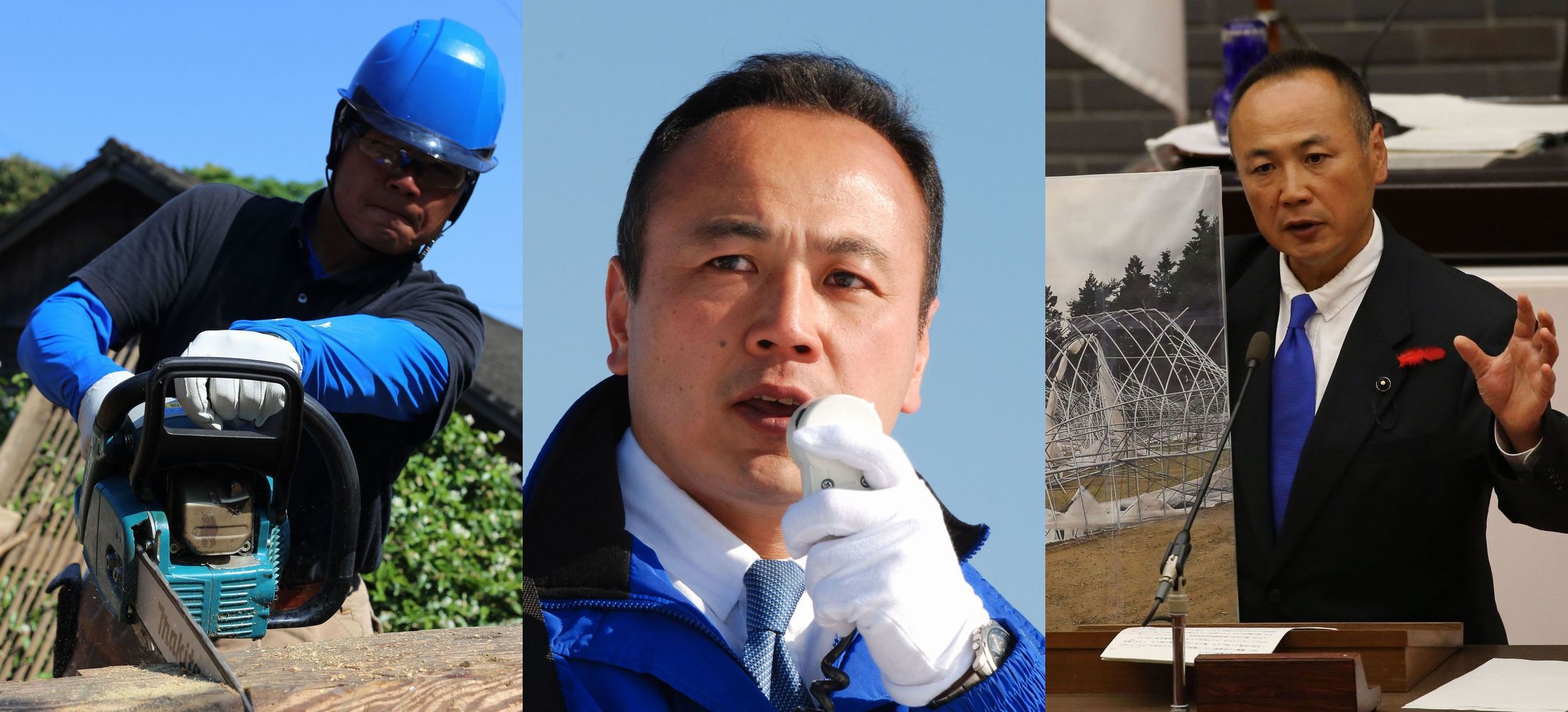



 国の来年度予算が内示され、医師不足対策にも161億円が提示されました。
国の来年度予算が内示され、医師不足対策にも161億円が提示されました。
 COP13で話し合われた『地球温暖化防止』。
COP13で話し合われた『地球温暖化防止』。 今日、森田実さんの講演を聞く機会がありました。
今日、森田実さんの講演を聞く機会がありました。

 今日の一考は「消防団員の不足」
今日の一考は「消防団員の不足」


 今日の一考は「緊急医療の確保」
今日の一考は「緊急医療の確保」 今日の一考は「限界集落」
今日の一考は「限界集落」 今日の一考
今日の一考 今日の一考は「医療施設の連携」について。
今日の一考は「医療施設の連携」について。 いじめ。
いじめ。