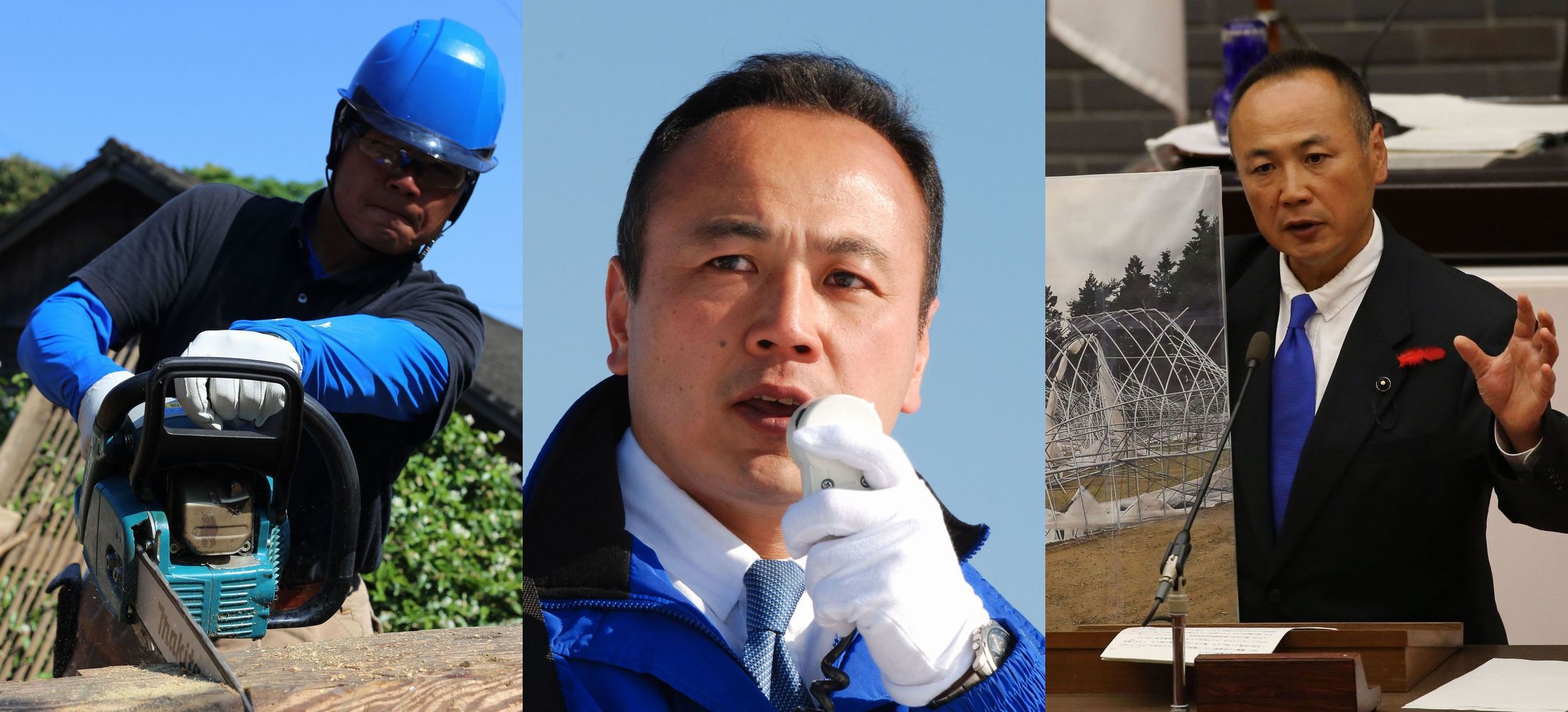災害になる時とならない時
 川上:サポートコミュニティ飛騨の川上哲也です。さて遠藤さん、今朝はビックリしました。
川上:サポートコミュニティ飛騨の川上哲也です。さて遠藤さん、今朝はビックリしました。遠藤:どうしたんですか?
川上:朝起きて鏡を見たら、髪の毛がえらい増えてて…。
遠藤:川上さん、ラジオだから見えないと思って…。
川上:エープリルフールですから、このくらいの嘘はいいかな…と。ということで、今日から新年度になりましたが、今年も宜しくお願いします。3月は卒業、退職そして転勤などいろんな別れもありましたけど、4月は入学や入社、新しい勤務地での仕事など、出会いも多い時期ですよね。
遠藤:ヒッツにも、新しいナビゲーターさんが入ってくださったんですよ。
川上:そうそう、さっき会いました。さてさて、年度始め、会社によっては今日が入社式という所もあると思いますし、職場によっては、このヒッツを聞きながら仕事をされてる所もあるようですから、何回かお話しした話にはなりますが、災害の基礎の基礎からお話しさせて頂きますね。
遠藤:お願いします。では、その「災害の基礎の基礎」はどんな話題を?
川上:今日はですねぇ、災害って、どんな時に起こるものなの?ということをお話ししますね。
遠藤:災害はいったいどんな時におこるものか? 地震とか水害とか台風とか、そういった災害がですか?
川上:まあ、そういった自然現象によって起こる被害なんですけど、どういう場合に災害になるか?が肝心なんですよね。災害になる時とならない時がありますからね。
遠藤:災害になる時とならない時?
川上:例えば、世界遺産の白川郷で、50cmの雪が積もったら、これは災害になるでしょうか?
遠藤:50cmというと、ひざ辺りか、それより少し上くらいですよね。それくらいなら、白川郷の皆さんにとっては、ちょっと多めかな…くらいの積雪じゃないですか?
川上:では、万が一ですけど、名古屋で50cmの雪が一面に積もったら、災害になるでしょうか?
遠藤:名古屋で50cmの雪が積もったら、道路の交通は完全にマヒしますよね。車は走れない、人も外に出られないなんてことになりそうですから、災害という呼ばれ方をするかも…ですよね。
川上:そうですよね。この場合、雪に対する備えをしているかしていないかによって、災害になるかならないか、違いが出てきてしまうんですよね。では、次に地震について考えてみましょうか。
遠藤:地震も、備えによって全く違うでしょうね。
川上:そうですよね。同じ震度の地震が襲ってきても、耐震性の高い家に住んでいる場合と耐震性の低い家に住んでいる場合では、被害の受け方が全く違いますし、家具の固定をしている場合と家具の固定をしていない場合では、家族のケガや家の被害状況も変わってきますよね。
遠藤:そうですよね。中越沖地震でも、耐震性の低い住宅が倒壊した割合が高かったって言われてましたものね。そして、中国四川の地震でも、耐震性の低い学校が倒壊して、子ども達の尊い命が奪われてしまったんですよね。
川上:そうなんですよね。備えによって、被害が全く違ってきますよね。中国四川の地震の場合でも、もし、学校や住宅が、震度6強や震度7に耐えられるものだったとしたら、あれだけの死者数になったかどうか…、遠藤さん、どう思います?
遠藤:たしか、9万人くらいの方が亡くなったんでしたよね。被災した家の写真を見たことがありますけど、耐震性の低い家が多かったなぁという印象があるんですけど…。
川上:そうでしたよね。レンガを積み上げてつくってある家が、鉄筋が入っていなかったためか、ガラガラッと崩れた感じのものが多かったと思いますけど、もし、あれらの家に鉄筋が入っていて、簡単に崩れるような構造じゃなかった場合、亡くなる方の数はどうなったでしょう?
遠藤:もちろん、少なくなりますよね。
川上:そうですよね。備えができていれば、災害で亡くなる方の数を、相当数減らすことができる…と言いますか、備えがしっかりしていれば、「災害」という呼び方をさせない状態にすることも可能になるんですよね。
遠藤:ということは、災害への備えは本当に重要ですよね。同じ自然現象が起きても、災害になる時とならない時があって、その分れ目は、備えができているかできていないか…なんですね。
川上:その通り…なんですが、残念ながら、耐震補強はなかなか進んでいませんよね。
遠藤:耐震診断を受けていない人も多いようですよね。実は、私の家もまだで…。
川上:あれま。この、耐震診断というのは、その住宅の持ち主が申請しないと耐震診断が行われないのですが、こういった行政側の「待ち・受け身」の姿勢だと、なかなか進みませんよね。でも、いろんな地域を見てみますと、例えば、木造住宅密集地などで、ここがふさがれると、避難路が失われることも考えられるなぁ…と思われるような所もありますから、こういった所については、自治体が、耐震補強重点地域を設定して、その地域については、自治体側から耐震診断を積極的に提案するとか、耐震補強に対する補助もかさ上げするとか、そういった攻めの対応も必要かと思いますよね。
遠藤:なるほど~。たしかにそうですよね。高山にも木造住宅密集地がありますし、阪神淡路大震災のように火災が発生すると、避難路の確保は非常に重要ですからね。
川上:これも備えのひとつですよね。さて、話を今日のテーマである「災害になる時とならない時」という話題に戻しますが、今日お話ししましたように、同じ自然現象が起きても、備えがしっかりしていれば、かなり災害を減らすことや、それが進めば、災害と呼ばせないレベルにまで抑えることができるということなんですよね。これを考えて、ぜひ災害への備えを考えて欲しいですよね。
遠藤:災害への備えを進めるには、まず何から手をつけるべきなんですか?
川上:いろいろありますが、先ずは、自分の命と家族の命をどう守るかを考えるべきだと思いますので、家族で防災について話し合ってみることから始めてみてはいかがでしょうか? ということで、来週は、家族で防災について話し合うべき内容についてお話しさせて頂きますね。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。